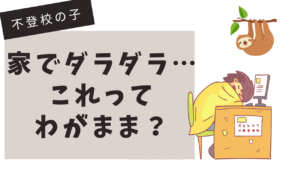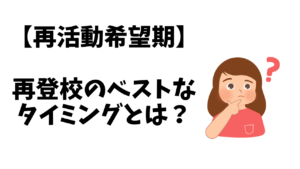長い連休明け。周囲の子が「明日からまた学校だね!」とワクワクしている一方で、我が子は暗い顔をして布団にこもる。そんな光景に、心を痛めるお母さんも多いのではないでしょうか。
この記事では、ゴールデンウィーク明けに不登校の子どもが感じやすいプレッシャーと、それによって起こる「登校刺激」の影響について解説します。親としてどう寄り添えばいいのか、同じように悩んできた母親の体験も交えてお届けします。
- GW明けは「登校刺激」が強まるタイミング
- 繊細な子ほど「休み明けの変化」に敏感
- 親の焦りがプレッシャーになることもある
- 子どもを守りながら、再登校のタイミングを見極める方法
GW明けに起こる「登校刺激」とは?|不登校の子が感じる見えない圧力
-2.png)
- ゴールデンウィーク明けは「周囲とのギャップ」が強く感じられる時期
- 登校刺激は“善意”からくる言葉でもプレッシャーになり得る
- 特にHSCなど繊細な子は休み明けの社会の変化に敏感
- 親の言葉が「プレッシャー」か「安心」か、大きな分かれ道になる
不登校の子が感じる「みんな行っているのに…」という焦り
ゴールデンウィーク明け、SNSやテレビで「明日から学校!」「新しいクラス楽しみ!」という声が飛び交うなか、不登校の子は強い孤独感に襲われます。自分が取り残されているような気持ちになり、「自分だけがダメなんじゃないか」と自信を失ってしまうのです。
この“ギャップ”を感じる瞬間が、休み明けに訪れる「登校刺激」の正体。親からのちょっとした一言も、社会からの無言のメッセージとして重なり、心の負担を倍増させてしまうのです。
登校刺激とは?休み明けに起こりやすい「逆効果」
登校刺激とは、直接的または間接的に「学校を意識させること」。たとえば、「明日から学校だね」という何気ない会話や、友達から届いた「明日またね」というLINEのメッセージすらも、登校へのプレッシャーとなることがあります。
親が励まそうとして口にする「がんばってみる?」という言葉も、繊細な子には「無理をしなきゃ」と受け止められ、逆効果に。「学校に行けるようになってほしい」という親心が、結果的に子どもの心を閉ざしてしまうリスクもあるのです。
実体験に学ぶ|私たち親子がGW明けに直面したこと
-1-1.png)
- GW明けの「ちょっとした声かけ」が息子の心を傷つけていた
- 学校の話題を封印することで、子どもが安心感を取り戻した
- 「ただ家にいる時間」も、回復のために大切なプロセスだった
- 学校復帰よりも「自分らしく生きられること」が最優先だと気づいた
何気ない「大丈夫?」が胸に刺さったGW明け
うちの息子は小学5年生から不登校になりました。新学期が始まると同時に教室に入れなくなり、自宅で過ごすようになっていたのですが、ゴールデンウィーク明けのある日、私が何気なく「学校はいつまでお休みするの?」と声をかけたのです。
すると、息子が口を閉ざし泣き出してしまいました。私は「応援していたつもり」だったのに、そのこころない言葉が「学校に行けていない自分を責められた」と感じたようでした。
「話題にしない」ことで子どもが安心を取り戻した
その出来事をきっかけに、私は学校の話を極力しないようにしました。「今日は天気がいいね」「お昼何食べようか」など、日常の小さな会話だけを大事にし、学校の話題を封印。
すると、息子は少しずつ穏やかになり、笑顔も戻ってきました。「学校のことを話されない」だけで、子どもはこんなにも安心できるのかと、私自身が驚いたのです。
親が焦らないと、子どもが動き出す日もある
ある日、息子が「ちょっと図書館に行ってみたい」と言い出しました。私は驚きつつも、「いいね!」とだけ返しました。これも、学校のことを話題にせず、子ども自身のペースを尊重していたからこそ出てきた言葉だと思います。
「登校再開」ではなく、「人と関わること」「外に出ること」から少しずつ始まる。それで十分だと、今なら胸を張って言えます。
GW明けにやってよかった工夫5つ
-2-1.png)
- 無理に外に連れ出さず、まずは家の中で「安心感」を育てた
- 日常のリズムを少しずつ整え、生活リズムを意識
- 親自身もストレスを抱え込まず、自分の時間を大切にした
- 子どもの「好きなこと」に寄り添った
- 「比較しない」「焦らない」「頑張らせない」を意識した
① 家の中で「安全地帯」を作る
我が家では、子どもが好きなぬいぐるみや本を置いた「自分だけのスペース」をリビングの一角に作りました。ここにいれば、安心できる。そんな“安全地帯”を作ることで、息子は心の休息を取れるようになりました。家の中で安心できる場所を整えることは、子どもが不安定なときにはとても大切です。
② 朝の過ごし方を「学校と関係なく」整える
生活リズムを戻そうと、「朝は起きなきゃダメ」と言いたくなりますが、我が家ではまず「朝起きたら好きなジュースを飲む」「布団から出るだけOK」という小さな目標から始めました。学校と無関係な“楽しいルーティン”を作ることで、無理なく体内リズムを整えられました。
③ 親も「1人時間」を大切にした
ずっと子どもと一緒にいると、親も疲れてしまいます。私は昼に15分だけコーヒーを飲みながらラジオを聴く時間を作りました。「自分もリラックスしていい」と思えたことで、子どもに対しても余裕を持てるように。親が機嫌よく過ごせることが、子どもにとっても何よりの安心になります。
④ 子どもの「好き」を伸ばす
ゲームやYouTubeばかり見ていると、つい不安になりますよね。でも私は「今は好きなことをとことんやらせよう」と切り替えました。ゲーム実況をノートにまとめる、図鑑を読んで動物のイラストを描く…。そこから「こんなこともできるんだ」と親子で小さな発見を楽しみました。
⑤ 他の子と「比較しない」姿勢を意識した
GW明けには「もう普通に登校してる子もいるのに…」と思ってしまいがちです。でも、心の回復にはそれぞれ時間が必要。私は「この子はこの子のスピードでいい」と意識して、周囲と比べるのをやめました。そうすると、私自身の心も軽くなり、子どもに対するプレッシャーも減っていきました。
GW明けの親の心がまえ|「登校」よりも大切なこと
-3.png)
- 「行かせる」ではなく「寄り添う」という発想に切り替える
- 回復には“安心感”と“時間”が必要
- 学校がすべてではないと知ることが、親にも救いになる
- 子どもが「自分らしく」いられる環境づくりを意識する
「がんばらせる」より「安心させる」ことが回復の近道
親としては、「学校に戻ってくれたら安心」と思ってしまいがちです。でも実は、「行かせようとすればするほど、遠ざかる」のが不登校の難しさ。子どもがまず必要としているのは、「無条件で受け入れてくれる場所」です。回復のきっかけは、“安心できる家庭”にあります。
「学校に戻るかどうか」がゴールじゃない
学校に戻ることだけがゴールじゃないと、私たちは気づきました。子どもが自分らしく、前を向いて生きていける力を身につけられれば、それが本当の意味での「自立」につながるのです。焦らず、一緒に“今”を過ごす。その積み重ねが、未来を作ると信じています。
【まとめ】GW明けは焦らず、子どもにとっての「安心」を最優先に
-4.png)
ゴールデンウィーク明けは、周囲の雰囲気とのギャップから不登校の子どもにとって心が不安定になりやすい時期です。
📌この記事のポイントおさらい
- GW明けの「登校刺激」は、子どもにとって大きな負担になることがある
- 親のちょっとした声かけが、子どもを傷つけてしまうこともある
- 子ども自身のペースを大切にし、「安心できる家庭」を整えることが回復への第一歩
- 学校よりも「子どもが自分らしく生きる力」を育てることが最も大切
親としても心配になり、つい声をかけすぎたり、焦ったりしてしまうもの。でも、まずは子どもにとっての「安心感」を守ること。それが何より大切です。
この記事が、今まさに悩んでいるお母さんお父さんの心を、ほんの少しでも軽くできたなら嬉しいです。
「大丈夫。今はそれだけで十分です。」
どうか、あなた自身のことも大切にしてくださいね。

-1.png)