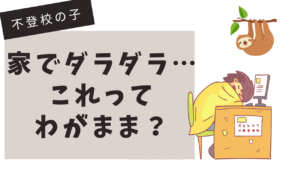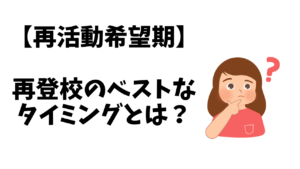新学期、「また学校に行けないかも…」という不安
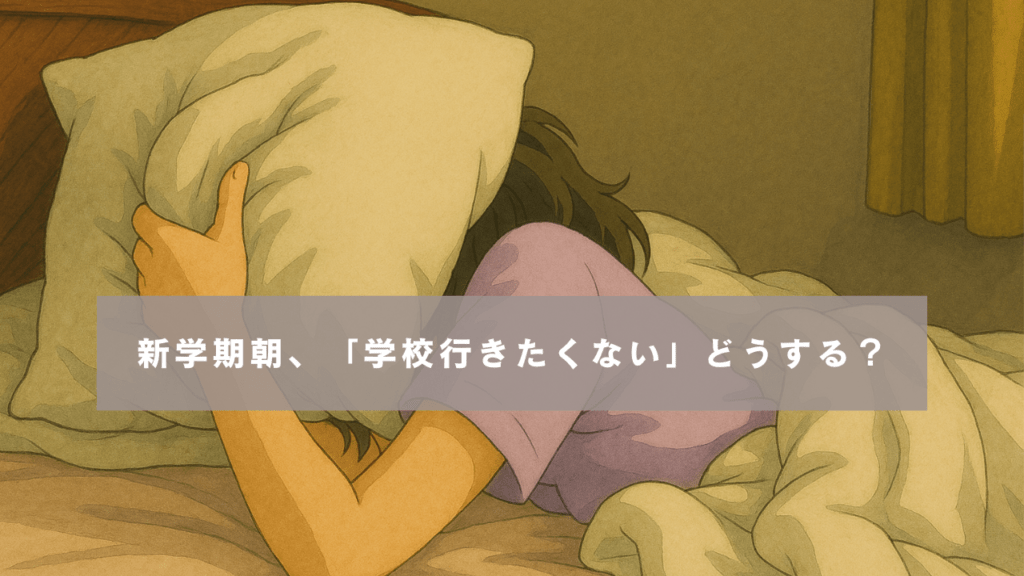
春休みが終わるころ、少しずつ空気が変わっていくのを感じます。
制服をそろえて、文房具を買って、子どもも少しずつ準備はしている――でも、ある朝ふと、うちの子がこう言ったんです。

「やっぱり学校、行きたくない…」
新学期の始まりは、本来なら「ワクワク」する季節のはず。でも、不登校気味のわが子にとっては、「またあの場所に行かなきゃいけない」「またつらい毎日が始まる」というプレッシャーそのもの。
私は、5年生のときから学校に行けなくなったHSC(ひといちばい敏感な子)の息子と暮らしています。
彼は新しい環境や人との関わりに、とても強い不安やストレスを感じるタイプ。新学期になるたびに、心と身体にブレーキがかかってしまうのです。
親として「どうしてあげたらいいの?」「本当に休ませていいの?」という悩みは、毎年春になると私たち親子に押し寄せてきます。
この経験が、同じように悩むお母さんの支えになればと思い、この記事を書きました。
- 子どもが学校に行きたくない理由は「甘え」ではなく、本人にも説明が難しい“心のSOS”かもしれません
- HSC(ひといちばい敏感な子)の特性を知ると、子どもの行動が理解できるようになります
- 不登校の子どもと向き合うママ自身が疲れきらないための、心の整え方をお伝えします
- 「親にできること」を知ることで、今日から少し安心して子どもと向き合えるようになります
新学期に「学校行きたくない」と言われる子どもの本当の気持ち
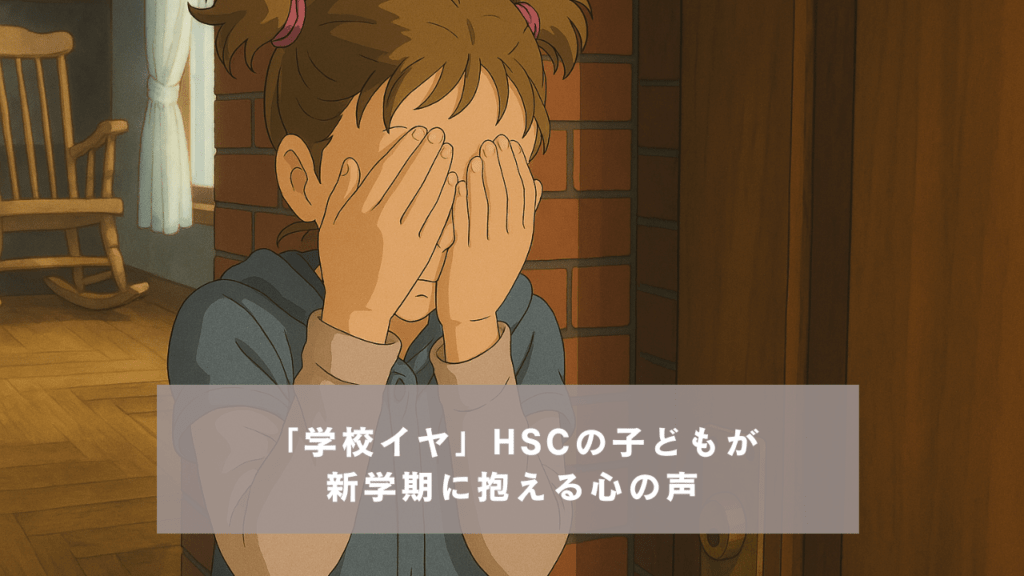
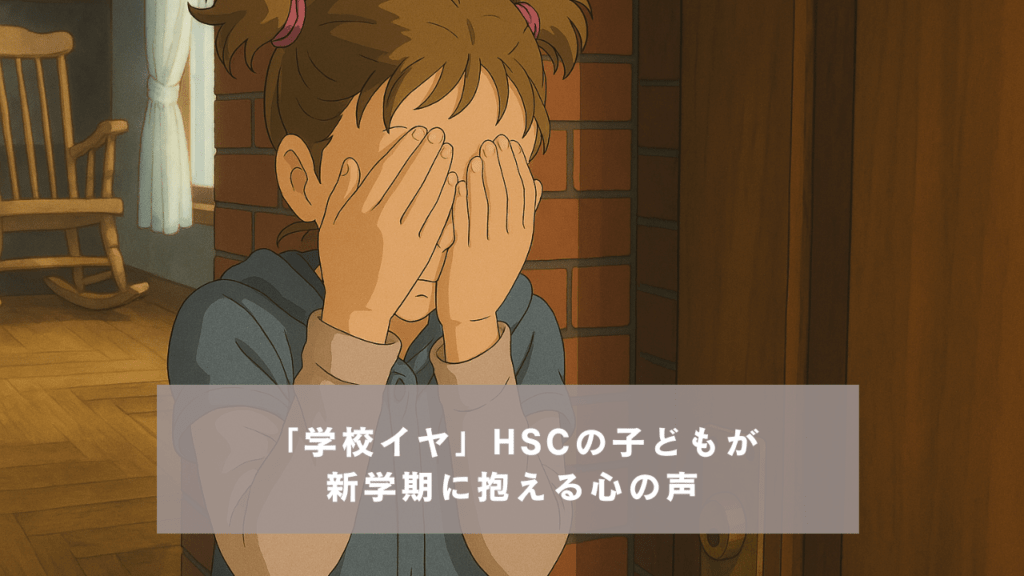
「行きたくない=怠け」ではない理由とは?
「新学期 学校 行きたくない」という言葉を子どもが発したとき、親としてまず思ってしまうのが、



「え、また?」
「周りの子はちゃんと行ってるのに…」
「このままでいいの?」
という不安や焦りではないでしょうか。
でも、「行きたくない」と言う子の多くは、「行かない」ことを選んでいるわけではありません。
実は、「行きたいのに行けない」という矛盾を抱えて、とてもつらい気持ちでいるんです。
たとえばうちの息子も、前日の夜にはランドセルをきちんと準備して、明日の時間割まで確認して眠ります。でも朝になると、無言のまま布団から出られない。そして小さく、「行きたくない…」とつぶやくのです。
その姿は、ただの怠けでも、反抗でもなく――
「どうしても無理」「怖い」「つらい」という心のSOSそのものでした。
子どもが言葉にできない「行けない理由」
親として、「なんで行きたくないの?」「何かあったの?」と聞いても、子どもはなかなか答えられません。
それは、自分でもその理由をはっきり説明できないから。
特にHSCの子どもは、次のような「目に見えにくいストレス」を抱えていることがあります。
- クラス替えや先生の変化への不安
- 大勢の人の中にいることへの圧迫感
- 小さな出来事を深く気にしてしまう
- 友達のちょっとした表情や言葉で傷つく
- 自分を責めやすく、「ちゃんとできない」と思い込みやすい
うちの息子も、ある年の新学期に「席替えがつらい」と言いました。
最初は「たったそれだけ?」と思ってしまいましたが、話を深く聞いていくと――



「後ろの子のため息が怖い」
「周りの声が頭に響いて集中できない」
「どこに座っても落ち着けない」
そんな理由が出てきました。
大人からすると些細に思えることも、敏感な子どもには「毎日耐えがたい苦痛」になるのです。
「うちの子はHSCかもしれない」と思ったら
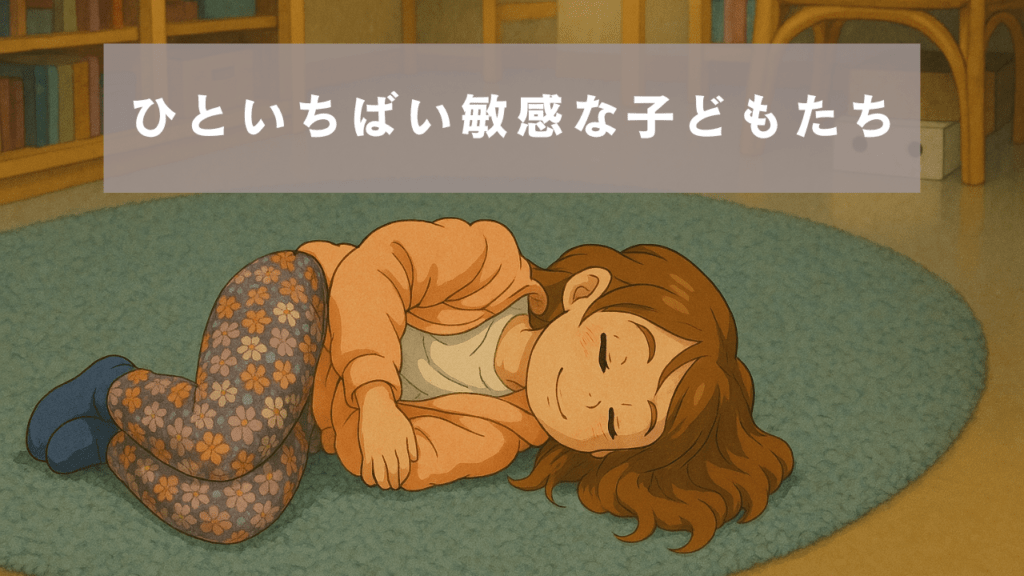
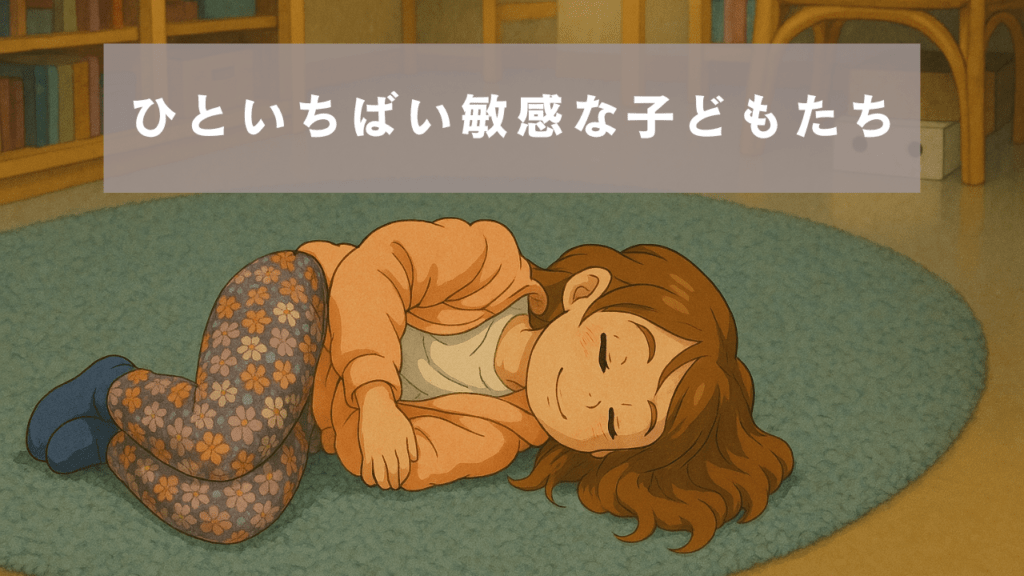
HSCとは? 〜ひといちばい敏感な子どもたち〜
HSC(Highly Sensitive Child)は、「とても敏感で繊細な気質を持った子ども」のこと。
日本ではまだ広く知られていない概念ですが、実は5人に1人の割合でHSCの子は存在するといわれています。
特徴としては、以下のような点が挙げられます。
- 音や光、匂い、人混みに敏感
- 他人の感情を強く感じ取ってしまう
- ちょっとしたことで深く傷つく
- 褒められても「もっと頑張らなきゃ」と思ってしまう
- 些細な変化にすぐ気づく(クラスの空気感など)
これらは「気にしすぎ」「わがまま」と見られがちですが、HSCならではの特性なのです。
「甘え」じゃない。キャパオーバーのサインかもしれない
HSCの子どもは、日常のすべてに対してとても注意深く反応しているため、
たった1日でもエネルギーを使い切ってしまうことがあります。
息子も新学期になると、いつもより早く起きて準備しようとし、学校では緊張を張りつめて過ごし、帰宅するとグッタリ。
新しい環境に適応しようと一生懸命がんばった結果、数日で心身ともに限界を迎えてしまいます。
「朝、起きられない」「頭が痛い」「お腹が痛い」といった身体症状も、心の負担からくるものが少なくありません。
親にできること:まずは“行かせようとしない”ことから
子どもを責めないことが、最大のサポート
「学校は行くべきもの」「このままだと将来が不安」
そんな思いがよぎるのは当然です。私も何度もそう思いました。
でも、まず大切なのは、“行かせようとする”ことを手放すことだと感じています。
不登校やHSCの子どもにとって、「学校に行けない」ことは本人も苦しんでいる現実。
その気持ちに寄り添うだけで、子どもはホッと息をつけるのです。
たとえば、私がよく息子にかける言葉はこうです:



「今日は行かなくてもいいよ」
「行けないのは悪いことじゃないよ」
「おうちでゆっくりしよう」
すると、ほんの少し表情がやわらぎます。
行けない自分を責めていた息子にとって、「認めてもらえた」という安心感が何よりの支えになったようです。
親自身が「優しくできない日」もあっていい
正直に言うと、私も毎日優しく接していられたわけではありません。
「なんで行けないの?」「また今日も休むの?」と、イライラしてしまう日もありました。
そんなときは、自分を責める前に少し立ち止まって、深呼吸。
「今日も息子と一緒に過ごせている」それだけでもう十分なんだと、自分にも優しく言い聞かせます。
親も人間。完璧じゃなくていいんです。
時には「もう限界かも…」と感じたら、誰かに話を聞いてもらったり、自分を甘やかす時間も必要ですよね。
「できること」に目を向けると心が軽くなる
「行かせる」ことが目標ではなくなったとき、私はこう考えるようになりました。
学校に行けない今、この子に何が必要だろう?
今、この子とできる“日常”はなんだろう?
たとえば――
- 朝ごはんを一緒にゆっくり食べる
- 散歩に誘ってみる(行けなくてもOK)
- 本を一緒に読んでみる
- ゲームの話をただ聞いてみる
ほんの小さな「関わり」から、子どもとの信頼関係が少しずつ深まっていきました。
行けない今も、確実に“成長”している
「うちの子、何もしてない…」と感じたら
不登校になると、「勉強してない」「家でダラダラしてるだけ」と見えてしまうこともあります。
でも、それは見た目の一部であって、内側ではものすごい葛藤と成長が起きているのです。
息子も、毎朝「行けない自分」と向き合いながら、どうすればいいか、自分なりに必死で考えていました。
ある日ふと、「今日、少しだけ外の空気吸ってみたい」と言ってくれた時は、本当にうれしかったです。
無理に動かそうとしなくても、子ども自身の中に「進むタイミング」がちゃんと訪れます。
それを信じて待つことも、立派なサポートです。
親の安心が、子どもに伝わる
HSCの子どもは、親の気持ちをとても敏感に感じ取ります。
だからこそ、親が不安になりすぎると、それも伝わってしまうんですね。
私も、「このままでいいのかな」と悩むことは今もあります。
でも、「大丈夫、息子にはちゃんと力がある」と信じることにしています。
不安になったら、ノートに気持ちを書くのもおすすめです。
「今日は笑顔で話せた」「一緒にお昼ご飯が食べられた」――
そんなささいな記録が、のちに大きな励みになります。
まとめ|「学校に行けない」ことは、終わりではなく“始まり”かもしれない
新学期、「学校行きたくない」と言う子どもの言葉に戸惑うのは当然です。
でも、それは「逃げ」でも「問題」でもなく、新しい生き方のスタート地点なのかもしれません。
大切なのは、
- 子どもの気持ちを「否定しない」こと
- HSCという気質を理解すること
- 親自身の心も大事にすること
- 今できる小さな関わりを続けること
焦らなくて大丈夫です。
どんな形であれ、親子で一緒に進んでいけば、それが一番の安心につながります。
この先もきっと、つまずく日や迷う日があるかもしれません。
でも、同じように悩みながら進んでいるママがここにもいます。
ひとりじゃないということを、どうか忘れないでくださいね。
💡もし今、言葉にならないモヤモヤがあるなら、「そのままでも大丈夫だよ」とお子さんにも、自分自身にも伝えてあげてください😊
きっと、少しずつ、風が変わっていきます。

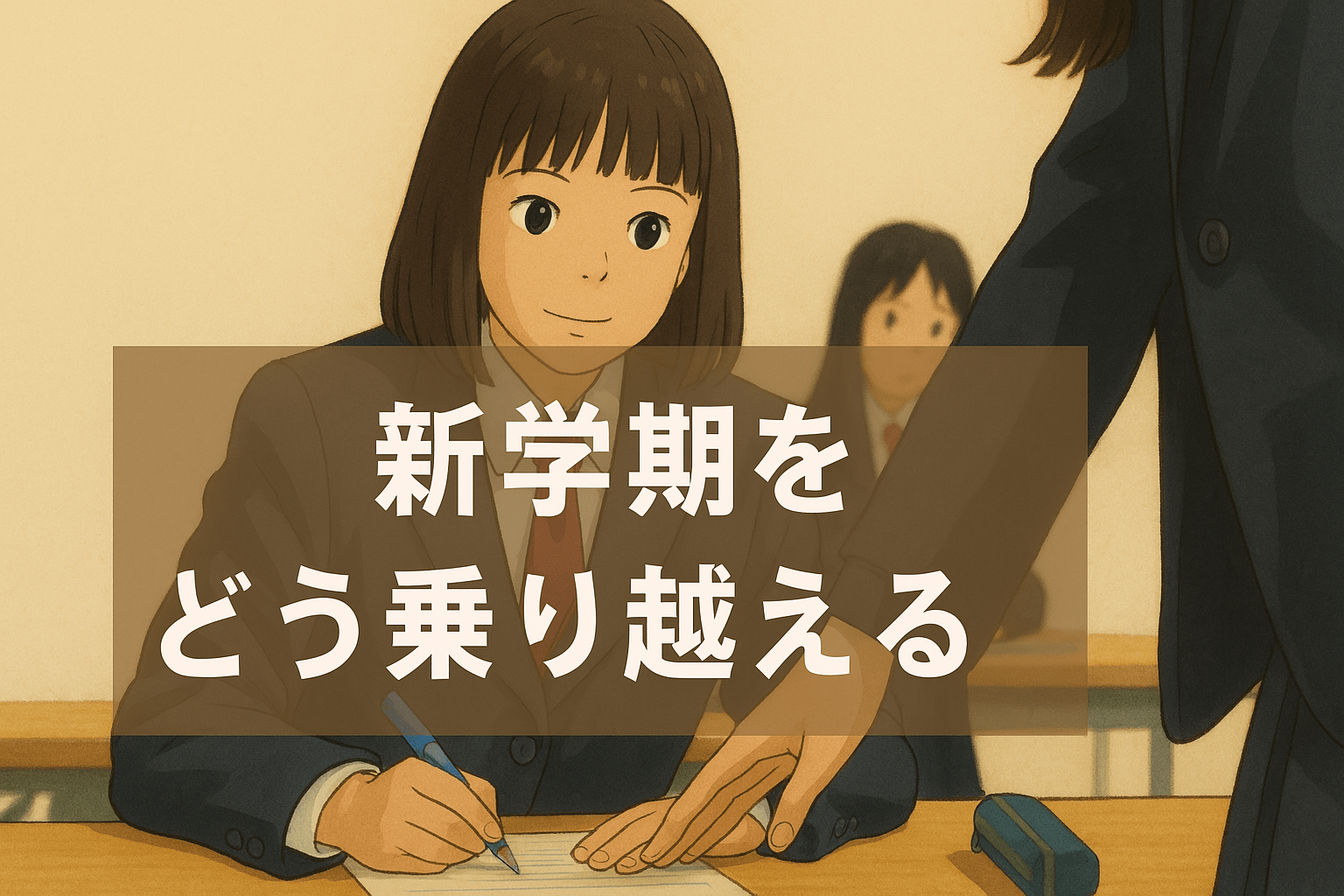
-1-300x225.png)